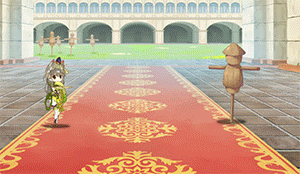|
Dieses Baums Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Giebt geheimen Sinn zu kosten,
Wie's den Wissenden erbaut,
中国原産のイチョウ科イチョウ属の落葉高木。
ヒノキに続いてようやく2人目の裸子植物のフラワーナイトであり、やはり花と言って良いのか怪しいほど地味な花を咲かせるが、
その代わり、秋になれば扇型の葉を鮮やかな黄金色に変え、燃えるようなモミジの赤と共に、日本の秋を美しく彩ってくれる。
その美しさに加え、大気汚染に強い、剪定しやすいなどの特徴から、日本国内ではあちらこちらで街路樹として植栽されている。
平成18年度末の国土交通省の調査によれば、その本数は57万本であり、サクラの49万本を超えて最も多く植栽されている樹種と言われている。
このように街路樹という印象の強いイチョウだが、長命な樹木としても知られており、日本各地に樹齢数百から千を超える「大銀杏」が点在している。
国内で最大のイチョウは、青森県の北金ヶ沢にある。樹齢千年を超えると言われる巨木は、高さ31m、幹周り22mにも達する。その威容はもはや一本の森。
また、このように幾星霜を経て巨大化したイチョウでは気根が発達し、枝から円錐状の突起が垂れ下がるようになることがあり、
この突起のことを俗に 『 乳 』 と呼ぶ。喜べ、お前らの大好きな乳だぞ。ただし雄株でも乳と呼ぶがな。
乳の発達したイチョウは、乳イチョウや垂乳根(たらちね)のイチョウなどと呼ばれ、安産や子育ての信仰対象となることも多い。
気根といえば、通常はマングローブなどの湿地帯の植物が呼吸や給排水のために発達させるものだが、イチョウが何故乳を発達させるのかはよく分かっていない。
イチョウの利用は街路樹に留まらない。例えば、その種子であるギンナン(銀杏)は、秋の味覚に欠かせないものとなっている。
果実だと思われていることも多いが、裸子植物であるイチョウは果実をもたず、種子と呼ぶのが正しい。硬い殻の内側にある仁(じん)の部分を食用とする。
独特の風味と食感が癖になるギンナンだが、困ったことに種皮の部分には強い悪臭があり、毎年シーズンになるとこの悪臭が問題となることもしばしば。
イチョウは雌雄異株なので、種子を作るのは雌株だけである。街路樹としては、そもそも種子を作らない雄株だけが選んで植えられているところが多い。
だが、古いイチョウ並木にはわりと雌株が植わっていたり、選別の際のミスでぽつんと雌株がまじっていたりするので一度雌株を探して銀杏拾いをみるの楽しいかもしれない。その際にビニール手袋などで手を保護しないと大変なことになるが
また、ギンナンは有毒であるということも忘れてはならない。食べ過ぎると神経の異常興奮を招き、痙攣などの中毒症状を起こすことがある。
その上、表皮は含まれているギンコール酸と銀杏の臭いの素である酪酸(らくさん)の影響で手を触れるとかぶれやただれを起こすので注意した方がいい。
中毒を起こす量の目安は、大人の場合は40粒以上、子供の場合は7粒以上とされている。実際に報告されているケースでも、10歳未満の子供の中毒が7割を占める。
子供にギンナンを食べさせる場合は食べ過ぎないように注意し、また5歳未満の特に小さな子供の場合は与えないほうが良いだろう。
イチョウの木材は生産量は少ないが、材質が均一で、加工性も良く狂いが少ない優良な木材である。昔から将棋盤や碁盤などに好んで用いられた。
油分を含み水はけが良いことや、表面がきめ細かく適度な柔らかさを持つことから、特に「まな板」の素材としては最高級とされる。「まな板にしようぜ!」
また、イチョウの木は含水率が高く、非常に燃えにくい。それどころか、火事になるとイチョウの木が水を吹き出して火を消した、という伝説まで存在する。
しかも、この水吹きイチョウの伝説はひとつだけではなく、東京の浅草寺と湯島聖堂、京都の西本願寺の大イチョウに、それぞれ似たような話が伝わっている。
この話もあながち真っ赤な嘘というわけでもなさそうで、水蒸気の層を作って火が燃え移るのを防いだ、と考えれば状況にはある程度合致するであろう。
「火事と喧嘩は江戸の花」と言われるほど火災が多かった江戸の町では、長年に渡り市民の間で様々な火災対策が講じられてきたが、
そのうちのひとつとして、火に強いイチョウの木を各所に植えることで延焼を防いでいたという。恐らく「火消し」の元ネタであろう。
我々にとってごく身近なイチョウだが、その正体は「生きている化石」とも称される、氷河期にほぼ絶滅したとされるイチョウ網植物の唯一の生き残りである。
イチョウの祖先が誕生したのは、今から実に2億7000万年も前の古生代ことで、恐竜さんたちよりも早くから地球上に存在していた。
中生代から新生代にかけて、ちょうど恐竜の繁栄に重なる形で、イチョウは北半球全域に分布を広げたことが化石などから分かっているが、
これはギンナンを恐竜たちに美味しく食べてもらえるように進化させ、種子散布を効率よく行うようになったため、とも言われている。
しかし、約6500万年前の巨大隕石の衝突が原因と目される大規模な気候変動により、地球上のあらゆる生命は大量絶滅を迎えることとなる。
地上を席巻したイチョウもこの大変革には抗いきれず、最初に北米、続いてヨーロッパ、そしてアジアという順で、徐々にその姿を消していった。
ところが、ただ一種のイチョウだけが長い氷河期を乗り切り、中国のごく一部で辛うじて生き残っていたのである。
そうして発見されたイチョウは人の手によって保護され、やがて中国全域、朝鮮半島、そして日本などに再び根を下ろすようになったと言われている。
時は変わって明治時代、日本政府は西洋の進んだ学問や文化を取り入れるため、「お雇い外国人」と呼ばれる外国人学者達を日本へと招いたが、
そのうちの1人、ドイツ人医師で「日本誌」の著者であるエンゲルベルト・ケンペルは、日本ではイチョウがそこら中に植えられていることにとても驚いたという。
何せヨーロッパではイチョウは何百万年も前に絶滅しているのだから、彼にしてみれば、恐竜が当たり前のように歩きまわっているのを見たような心地だったのかもしれない。
ケンペルがイチョウの詳細なスケッチを記し、本国へと持ち帰ったことで、アジアで細々と生き残っていたイチョウの存在が世界に知られることとなる。
この時に名前の誤植があり、本来なら"Ginkjo"(ギンキョー、銀杏の音読み)とするはずが、誤って"Ginkgo"(ギンコ)と伝わってしまった。
この誤植が結局訂正されなかったため、イチョウ属の学名は現在でもGinkgoのままになっており、英語などでもそのまま"Ginkgo"と呼ばれている。
またケンペルはイチョウの種子も持ち帰っていた。イギリスのキュー植物園で栽培に成功すると、イチョウはヨーロッパ各地へ広まっていった。
人類は多くの種を絶滅に追いやってきた、というのは紛れも無い真実だが、一方でイチョウのように人の営みに救われた生物も、確かに存在する。
人もまた生態系の環の中に組み込まれた一種の動物であり、決して特別な支配者などではない、ということを忘れてはならないだろう。
尚、今でもイチョウはIUCNレッドリストにて絶滅危惧IB類に指定されている。日本にいると実感が湧きにくいが、とても貴重な樹木なので大事にしよう。
| ![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/logo1.jpg)
![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/logo1.jpg)