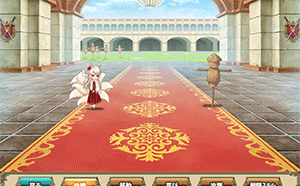|
緋色の花弁 眠らせましょう
ほら 虚無が飛来する 静かに瞳を閉じる
眠れ眠れ緋の華よ
ヒガンバナ(彼岸花) 学名:Lycoris radiata (L'Hér.) Herb. var. radiata 別名:マンジュシャゲ(曼珠沙華)
オシャカバナ(出典:”彼岸花の別名”)
団長さんで『リコリス』という単語を聞いたことがある人なら察してると思うが
『リコリス』は『ヒガンバナ属』の花を総称した言葉であり、ヒガンバナ属に属するヒガンバナも、リコリスの仲間である。出典・想いを贈る 花言葉(書籍)
ユリ目ヒガンバナ科リコリス亜属 Liliales Amaryllidaceae Lycorisヒガンバナ属の系統
クロンキスト体系の分類ではユリ科とされていた。出典ユリ目(ウィキペディア)
種小名のradiataは、後置するラテン語形容詞で「放射状の」を指している。Weblio英和和英事典「radiata」
英名:cluster-amaryllis・hurricane lily・red spider lily
・red spider lilyはリコリス自体がspider lilyと呼ばれてる事から頭に花の色(赤・Red)を付けてred spider lilyとなった説が多い。
・ hurricane lilyはヒガンバナの咲く時期からと思われる。
・cluster-amaryllisは何時ごろから言われだしたのか不明だが
”アマリリス(ヒガンバナ科ヒッペアストルム属 Hippeastrumの植物の総称)”が”集団(cluster)”で固まっている様に見えた。という説が多いようだ。
出典・人生みんな!楽しく過ごそう!
原産地:中国の揚子江から南あたり
ヒガンバナがどのようにして日本で群生したかの経緯については、未だ憶測の部分が多く、謎に包まれている。出典・筑波実験植物園 植物図鑑
参考:キツネノカミソリ学名:Lycoris sanguinea Maxim. var. sanguinea
分類:ユリ目ヒガンバナ科シマンタス亜属 Liliales Amaryllidaceae Symmanthus
種小名"sunguinea"は「血のように赤い」を意味するラテン語"sanguineus"の女性形。
歩き続ける彼岸花咲き続ける。
ヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草。秋の彼岸の頃に咲かせる、燃えるような赤い花が印象的である。
花言葉はあきらめ、悲しい思い出とあまりいい意味ではないものが多いが、
再会、想うはあなた一人、また会う日を楽しみに、と別の面を持ち合わせている。
日本国内では全国的に分布しており、群生していることもあってよく目立つ花でもあるので、秋の風物詩として馴染み深い。
花期に入ると、何もない地面から30~50cmの高さにもなる花茎を突然伸ばし始め、その先端に花をつける。
花は6枚の強く反り返った細長い花被片を持ち、5~7個程度の花を外向きに輪生させるため、無数の花弁を持つひとつの大きな花に見える。
ヒガンバナといえば赤色の花というイメージが強いが、稀に白花の変異を生じる。また近縁種にそっくりな姿で黄色い花のショウキズイセン、ピンクのナツズイセンなどがある。
ショウキズイセンとヒガンバナは交雑が可能だが、不思議なことにこの自然交雑種は白い花になり、シロバナマンジュシャゲと呼ばれる。
日本国内のヒガンバナに変異が現れるのは非常に稀(後述)なため、白いヒガンバナが群生しているのを見かけた場合、ほぼ間違いなくこいつである。
「ジメジメした暑い空気って嫌になるわぁ」と仰っている通り、過湿を嫌うが、元が丈夫なので見ての通り結構どこにでも根付く。
暑いのがどれくらい苦手なのかというと、夏になると葉を枯らして休眠するレベル。ヒガンバナは冬眠ではなく夏眠するのである。
一般的に植物は春に芽生え、夏に光合成をして栄養を作り、寒い秋から冬にかけては休眠するという生活環を持つが、
ヒガンバナはこれとは全く逆で、秋に休眠から目覚めるなり花を咲かせて繁殖活動(意味深)に勤しみ、冬の間に葉を茂らせて光合成をする。
春に周囲の植物が目覚め始めると、ヒガンバナは彼女たちの生存競争から逃げるように、葉を枯らして秋までの休眠に入るのである。
「葉見ず花見ず」というように、花があるときは葉を出さず、葉があるときは花を出さないというヒガンバナ特有の性質は、この生態による。
日本全国に分布しているヒガンバナだが、本来日本に自生する植物ではなく、中国の揚子江付近が原産の帰化植物とされる。
日本にやって来た経緯には諸説あるが、紀元前に中国から稲作とともに伝来し、人の手によって各地に植えられ、分布を広めたと考えられている。
その根拠として、日本国内のヒガンバナは全て遺伝的に同一なクローンであり、染色体数が3n=33の三倍体であることが挙げられる。
三倍体の植物は種子を結実できないため、種子散布を行って分布を拡げることはできないが、
球根などで自らのクローンを作る能力には長けているため、株分けによって容易に増やすことができる。
また、日本のヒガンバナは人里を中心に分布しており、山中などではほとんど見られないことも、人の手で植えられたことを示唆している。
では何故人々がヒガンバナをあちこちに植えたかというと、ヒガンバナの以下のような性質を生活に役立てていたためと言われている。
- ヒガンバナの鱗茎は有毒だがでんぷん質に富むため、毒抜きをすれば貴重な食料となった。
- 田畑をモグラなどから守るために有毒な植物を植えた。同様の理由で墓地にも植えられるようになった。
- 根が土を固く締まらせるという性質があるので、土手や畦道の土を固めるのに役立った。
- ヒガンバナの根から分泌される化学物質は、他の植物の成長を抑制するアレロパシー作用がある。
この作用はキク科植物に有効だがイネ科植物には効きにくいので、雑草を選択的に駆除することができた。
この説に対する主な反論としては、有史以前は無人であった孤島にもヒガンバナが分布するため、もともと自然分布していたとする説や、
これだけ人里に身近な花にも関わらず、平安以前の文献にヒガンバナの名が全く見られないため、伝来したのはもっと後だとする説がある。
万葉集には「路の辺の いちしの花の いちしろく 人皆知りぬ わが恋妻は」という柿本人麻呂の歌があり、
「いちしの花」と歌われているのがヒガンバナのことである、とも言われているが、これひとつだけというのも変な話ではある。
この歌の意味は「道端に目立つように咲いている『いちしの花』のように、私の恋心は皆にバレちゃったんだなぁ」といったところで、
「いちしろく」とは「著しく」の意であり「いちしの花」はとにかく目立つ花であるということは間違いないらしい。
かつては農業上重要な植物として扱われていたとされるヒガンバナだが、中近代における扱いはそれとは大きく異なる。
曰く「死人花」「幽霊花」「捨子花」など、ヒガンバナは不吉な花という側面を強く持つようになったのだ。
この事実もまた、ヒガンバナの伝来は室町時代以降であり、寺院が人里に広めたのだという後期伝来説の根拠でもある。
先述のように、土葬した遺体をモグラやネズミなどの動物から守るため、墓地にヒガンバナが植えられたことや、
有毒であるということからこうしたイメージが作られたと思われるが、具体的なきっかけはよく分かっていない。
ともあれ、一度根付いてしまったものは中々払拭されることはなく、現在に至るまで不吉な花という認識は依然として強い。
このようなイメージは日本固有のものであり、ヨーロッパなどでは美しい花が好まれ、古くから観賞用として育てられていた。
最近では海外で品種改良されたヒガンバナが、名前も学名の「リコリス」に改めて園芸用として流通しており、じわじわと人気を取り戻してきている。
一方でそのタブー感故か、妖艶とも言うべきこの花の魅力に取り憑かれる者も多く、特に思春期に特有の病気を抱えた人々には熱烈な人気がある。
興味深いことに、英語版wikipediaのCultural Referencesの項を見てみると、明らかに最近の日本のanimeやmangaへの言及が多い。
欧米ではヒガンバナは単なる園芸植物に過ぎないのに対し、日本では象徴的な意味を持つ花として特別視されているということが窺える。
兎にも角にも、今も昔もヒガンバナは何かと一目置かれる花であり続けているのである。
「彼岸花」というアレな名前や諸々の迷信も相まってか、有毒であることがよく知られている数少ない植物でもある。
ヒガンバナはリコリンやガランタミンなどのアルカロイドを含み、全草が有毒だが特に球根に多く含まれる。
神経毒性が強く、摂取すると嘔吐、下痢、麻痺、痙攣などの症状が表れ、最悪の場合中枢神経の麻痺を起こし死に至る。
と言われているのだが、毒草として有名な割には特に致死性が高いわけでもなく、球根を数個食べても嘔吐を催す程度である。
主要な成分であるリコリンの経口摂取時における半数致死量は、マウスの場合10700mg/kgと報告されており、
意外と毒性は強くない、というか弱い、弱すぎる…食塩より安全とまで言われると流石に怪しげである。
資料によっては180mg/kgというものもあるが、いずれにしても毒性は強くない。というか何を信じたら良いものか。
リコリンは水溶性であるため、球根をよくすり潰して水に長時間晒すことで無毒化でき、飢饉などのときは非常食にもされた。
毒抜きが不十分で中毒死することもあったと言われるが、恐らく栄養失調で身体機能が弱っていたことや、
長期間常食したために体内に毒物が蓄積されたことなど、副次的な要因が幾つか重なった結果ではないか、と思われる。
一方でガランタミンの半数致死量はマウスで25mg/kg、ラットで76.7mg/kgという数値だが、含有量はリコリンより遥かに少ない。
ガランタミンは脳内のアセチルコリン濃度を高める作用のため、アルツハイマー病の治療薬として1日8mgの量が処方されていたりもする。
また、リコリンには強い催吐作用があるため、大量摂取してもほとんどが吐き出されてしまい、重篤な事態には陥りにくい。
むしろ、毒を吐き出させるためにヒガンバナの毒を飲ませる、なんてこともかつては行われていたらしい。
ヒガンバナが毒草であることは間違いないが、ギョウジャニンニクに成り済まして問答無用で殺して回るどっかの1号とは違い、
「私を食べたら危ないわよ?次からは気をつけてね?」と、ちゃんと教えてくれるいい子なのである。
このように、美しい花というだけでなく、有用植物として、不吉な花として、毒の花として、
様々な側面を持つヒガンバナは、その異名の多さでも際立っており、日本一多くの名前を持つ花とも言われている。
その数は72通りなどという生易しいものではなく、少なくとも数百、ある調査によれば千を越えるとも。とにかく多すぎて正確な数は不明。
中でも特によく知られているのは「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)」という名前であろう。
曼珠沙華とはもともと法華経などの仏典に現れる花であり、サンスクリット語の"manjūṣaka"の音写である。
本来の曼珠沙華は天界に咲く花であり、天人がこの花を下界に降らす時、これを見たものは一切の罪業から離れられると言われている。
しかし、曼珠沙華は白色柔軟の花とも伝えられており、仏画や仏像にもヒガンバナを描いたものが無いことからも、
ヒガンバナを曼珠沙華と呼ぶのは、あくまで後世の後付であると考えるべきであろう。
他に特にピックアップしておきたいのは「狐花」や「狐の松明」「狐の簪」という名前である。そう、狐である。
ヒガンバナは何かと狐に関連付けられることが多い。同じヒガンバナ科にキツネノカミソリなんて花もあったりする。
狐といえば、このキャラクターのモチーフになっている「九尾の妖狐」。
日本でも傾国の美女、玉藻前の伝説が有名だが、元々は中国の神話に描かれる妖獣である。
進化後のヒガンバナが中華風の衣装を身につけているのは、中国を原産とすることと、中国の九尾伝説に由来するものと思われる。特定の世代の団長にはお馴染み蘇妲己ちゃん。
ついでに言えば、進化前の巫女服はお稲荷様からの連想、いわゆる狐巫女であろう。
それは私のおいなりさんだ
さらに前二つの九尾伝説よりも認知度は低いが、実はインドにも華陽婦人という九尾伝説が残っていたりする。ここでも権力者の男をたらしこみ、好き放題振舞っていたが、ある名医に正体がバレてインドから逃げたそうだ。この三人は時として同一の妖怪として見られる場合がある。この場合、中国→インド→日本と逃げて行き、日本で成敗されたという筋書きが多い。
また、中国神話での九尾は主に人を食らう悪者として描かれるが、一方で世の平安を迎える吉兆である瑞祥とされることも多い。
狐に例えられ、相反する側面を持ち、その美しさで人を魅了してやまないヒガンバナに、九尾というキャラクターはうってつけなのである。
…団長の皆様も傾国しないように気を付けて。
| ![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/logo1.jpg)
![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/logo1.jpg)