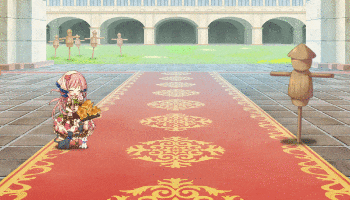|
彼は女の顔の上の花びらをとってやろうとしました。彼の手が女の顔にとどこうとした時に、何か変ったことが起ったように思われました。
すると、彼の手の下には降りつもった花びらばかりで、女の姿は掻き消えてただ幾つかの花びらになっていました。
そして、その花びらを掻き分けようとした彼の手も彼の身体も延した時にはもはや消えていました。
あとに花びらと、冷めたい虚空がはりつめているばかりでした。
春に匂う花は数あれど、彼女ほどの気品と風格を持った花はいかほど存在するだろうか。
ウメなどの日本の春を代表する数多くの花、それらの女王として君臨するサクラは、バラ科サクラ属のうち、サクラ亜属に属する落葉広葉樹の総称である。
春に白から薄紅、紅色の花を溢れんばかりに咲かせる姿、そして花弁を吹雪のように散らす姿は、日本人の心の原風景と言っても過言ではないだろう。
毎年シーズンに差し掛かると、靖国神社境内の標本木の様子や、サクラの開花を予想した桜前線などの情報が各種メディアで報道され、人々の関心を集める。
これほど人々に注目され、日常の話題に上ることのある花といえば、サクラを置いて他に無いだろう。
日本国内だけでもヤマザクラ、カンヒザクラ、エドヒガンなど、かなり多数の種や園芸品種が存在し、地域固有種も少なくない。
単にサクラといった場合、人間の生活圏内に極端に多く植樹されている、ソメイヨシノを指すことが多い。
ソメイヨシノはエドヒガン系とオオシマザクラとの交配種で、江戸時代末期に誕生したと言われる、意外と新しい品種である。
「染井吉野」というからには古くからの桜の名所、大和国の吉野との関連がありそうな気がするが、
実際には染井村という、当時の東京都巣鴨近辺にあった村で、ある植木屋が「吉野桜」の名でこの木を売っていたのが始まりである。
恐らくは「吉野の里のように見事なサクラ」といった意味なのだろうが、どうも園芸業界における流通名の紛らわしさというのは江戸時代からの伝統であるらしい。
「吉野桜」が人為的に品種改良されたものなのか、自然交配で生まれたものを植木屋が偶然見つけたのかは定かではないが、
もし偶然見つけたのであれば、恐らく自生地はオオシマザクラとエドヒガンの植生が重なる伊豆半島周辺である可能性が高く、
少なくとも吉野原産の種というわけではなさそうである。ちなみに現在でも吉野のサクラはソメイヨシノではなく、ヤマザクラの仲間が主である。
明治時代になってから、「吉野桜」は吉野のサクラではない、ということが藤野寄命(ヨリ☆ナガ)という人の調査によって明らかにされると、
やっぱり「吉野桜」という名前は不適切だし誤解を生みかねない、ということで「ソメイヨシノ」の名が改めて与えられた。
どうせなら「染井桜」にでもすればよかったのに、何故人は同じ過ちを繰り返してしまうのか。
花は薄紅色、花弁が大振りで形が整っている。葉が出る前に花が咲くので、満開時の見栄えが良い。
また、他の品種と比べて成長が早く、若木のうちに花を咲かせるという性質は、特に戦後復興期におけるソメイヨシノの爆発的人気に繋がった。
ソメイヨシノは同種間で種子を結実することができず、現在植樹されているソメイヨシノはほとんどが挿し木や接ぎ木によるクローンである。
そのため個体差による開花期のズレが極めて小さく、一斉に花を咲かせ、散らす様子も見た目の華やかさに一役買っている。
ただし、生物学に造詣ある団長ならお気づきであろうが、ほとんどがクローンということは、遺伝的多様性に乏しいということである。
もし感染症の流行や大規模な気候変動が起こった場合、すべての個体が耐え切れずに全滅する可能性もあり、特に未知の病原菌は脅威となる。
また、サクラ全般に言えることであるが、傷口が腐敗しやすく、小さな傷が原因で枯死してしまうことも少なくない。
桜切るバカ、梅切らぬバカという庭師の教訓がそれを如実に物語っている。
そんなデリケートな木なので、花見などの際はサクラさんを傷つけたりしてしまわないように注意しよう。
木に傷を付けるのは勿論厳禁、バーベキューの煙やゴミの放置なども樹木に悪影響を与えます。マナーを守って楽しいお花見を。
サクラといえば、サクラの花の下で小宴会を催す「花見」も日本の伝統文化のひとつとなっている。団長諸兄は今年、どちらへ花見に行かれますか?
花見の起源は古い。ヤマザクラなどは有史以前から日本に自生しており、古代人がそれを愛でていた可能性は高く、
実際、万葉集や古今集といった古い文献にも、サクラの花に関する記述は少なからず見られる。
古代において、サクラの花は鑑賞の対象というよりは、その年の稲作を始める時期を知らせる花として、農耕民族にとって重要な花であった。
故にサクラには、山の神であり農耕の神でもある「サ神」という、古事記に記された八百万の神々よりも古い土着神の一柱が宿ると信じられていた。
サクラの「サ」とはサ神のこと、「クラ」とは神座のことであり、「サクラ」とは即ち「サ神様の依代」の意味であったとされる。
「サクラ」の木の下で「サ神様」に「おサケ」と、山と海の「サチ」を「サカナ」として「ササげて」、今年の豊穣をお祈りし、
人々は神様が手を付けられなかった「おサがり」をいただきながらお祭り騒ぎをする、というのが古代における花見であり、
それは花を鑑賞するというよりも、列記とした神事のひとつであり、故に花見というよりは「花祭り」とでも呼ぶべきものであった。
花祭りといえば、仏教における灌仏会、4月8日の釈迦の誕生日のお祝いのことを「花祭り」と呼ぶこともあるが、
これは本来仏教とは無関係なサ神信仰の祭事が、同時期に行われる灌仏会と融合した結果生まれた、ある意味での神仏習合の産物であるとも言われている。
現在のように、花を鑑賞する花見がひとつの行事として確立したのは、奈良時代の貴族の文化に由来するとされる。
しかし、その頃は花見といえばサクラではなく、ウメの花を眺めることであった。
旧暦における新春のころに花期を迎えるウメは、春を告げる花として持て囃されたということと、
遣隋使達が中国から持ち帰ったウメが、ハイカラで大陸びいきな貴族の目に止まったのだろう。
また、当時サクラといえば山奥に咲くヤマザクラの仲間が主であり、現在のように気軽に鑑賞できるものではなかったとも考えられる。あいつら引きこもりだし
花見の対象がサクラへと移り変わったのは、平安時代から鎌倉時代にかけて、武士の台頭と貴族の衰退に時期が一致する。
気品を感じさせるウメの佇まいに対し、潔い散り際を見せるサクラの花は、田舎上がりの豪気な武士たちに好まれた。
本来、武士とは地方の豪農が急激に力をつけたものだということを考えれば、元々農民であった彼らにサクラを愛する精神があったとしても不思議ではない。
またその儚さが「諸行無常」「色即是空」に代表される仏教の精神や、わびさび、幽玄の美学など、武士たちの流行に結びついたのだろう。
あるいは、貴族に対する反骨精神といったものが、武士独自の文化を生み出す原動力にもなったのかもしれない。
花見の文化が庶民に大きく広まったのは江戸時代である。江戸時代の日本は世界有数の園芸大国でもあった。
ソメイヨシノなどの観賞用のサクラが品種改良によって数多く生み出され、各地の公園や寺院などに植えられると、市井の人々の目に止まるようになった。
現在のように、近所の河原でちょっとお酒とお菓子を持ち寄って、なんていうスタイルは、この頃に生まれたものといえよう。
毎年の日本人の楽しみとして、長く親しまれる花見だが、近年では酒乱騒ぎやゴミの散乱、近隣住民とのトラブルなどの問題も頻発している。
くれぐれも、団長諸兄は花を愛する心を第一に、マナーを守って楽しいお花見を。
中世の和歌、舞踊、能楽、江戸の落語や歌舞伎、小唄や地唄、そして明治、大正以降の小説や歌謡曲、
現代の映画や漫画、アニメ、ゲームに至るまで、いずれにおいてもサクラをモチーフとした作品は多い。お花だって当然その中のひとつなのである。
純粋に花の美しさと儚さを讃えるものもあれば、その美しさの中に妖艶とも、狂気とも取れるものを見出したものも少なくない。
”櫻の樹の下には屍體が埋まつてゐる!”――唐突に物騒な文句で幕を切る、梶井基次郎の「櫻の樹の下には」は、ダーク系桜文学の先駆けであろう。
人との関わりが長いだけあって、1本のサクラの樹に寄せる思いも、時と人によって千差万別に異なる。
花見散歩も悪くはないが、部屋に篭って青空文庫等で様々な「サクラ」を鑑賞してみるのもまた、面白い発見があるかもしれない。
| ![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/logo1.jpg)
![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/logo1.jpg)